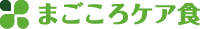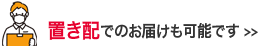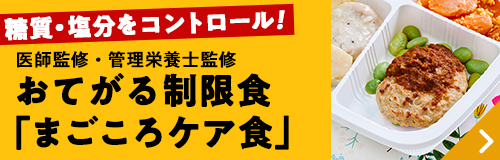関西では夏に欠かせない魚、ハモ。赤い梅肉酢を落とし、ボタンの花のようにひらひらと広がった「ハモの落とし(湯引き)」は、特に夏の京都、大阪では欠かせない食べ物。脂があるのにさっぱりとした姿からは想像できない豊富な栄養素を秘め、口元を見てわかる通り、獰猛な魚でもあります。今回はそんなハモの栄養価やおいしいレシピをご紹介します。
目次
ハモはどのような魚?
ハモはウナギ科ハモ目の魚で、主に西日本各地の瀬戸内、太平洋側で水揚げされ、中国、韓国からも輸入されています。大きいものは2m近くまで成長し、歯がとても鋭く、魚類やエビ、カニなどを捕食する獰猛な魚です。
「ハモ」という名前も、「食む(はむ)」「咬む(かむ)」に由来しているといわれています。
詳しい生態についてはまだ研究途上ということですが、太平洋から産卵のために瀬戸内海に入ってくるのではないかとされています。「ハモは梅雨の水を飲んで旨くなる」と言われ、初夏から夏にかけて脂がのり、旬を迎えます。
また、背骨から伸びる小骨が枝分かれしているうえにとても本数が多くて固く、そのままで煮ものや焼き物にしたり、すべての小骨を抜いたりすることも困難なことから「骨切り」という技術が生まれました。関西の和食界では、「ハモの骨切りができてようやく一人前」と言われます。
その獰猛な性格や顔つきからは想像できないほど、上品で甘味があり、臭みがなく、さまざまな料理で楽しむことができる魚ですが、骨切りした身をさっと湯通しし、梅肉酢を添えて食べるのが定番です。
関西では特に愛されている魚で、大阪天満の天神祭り、京都の祇園祭の頃、ハモを食べて夏を感じます。
9月に入ると産卵を終え、身は痩せて味が落ちますが、晩秋を迎える頃には再び脂を蓄え、全体に金色を帯びた体色へと変化します。これを「落ちハモ・金ハモ」といい、11月初旬にかけて、再び旬を迎えることになります。
ハモの栄養価とは?
① たんぱく質
たんぱく質は三大栄養素の一つで、標準的な成人の場合、体重の約1/5を占め、筋肉や血液に含まれているだけではなく、エネルギー源としても利用されています。また、常に分解・生成を繰り返しているため、毎日取り続ける必要があります。
生のハモ100gあたり、22.3gのたんぱく質を含んでいます。
② カルシウム
小骨を骨切りして食べるハモには、多くのカルシウムが含まれています。
カルシウムは私たちの体内に含まれる総量のうち、99%が骨や歯に蓄えられています。残り1%は血液や体液中に含まれ、止血を助け、神経伝達や筋肉の動きを促し、生命活動の維持を行う役割を果たす栄養素のひとつです。
生のハモ100gあたり、79mgのカルシウムが含まれています。
③ ビタミンD
ビタミンDは脂に溶けるビタミンの一つで、食べ物から取るほか、陽の光を浴びることで、体内で作り出すこともできます。ビタミンDは体内でカルシウムの吸収を促進し、骨を丈夫にする働きがあります。不足すると骨や歯の形成が上手くいかなくなり、くる病や骨軟化症を引き起こすことがあります。
生のハモ100gあたり、5㎍のビタミンDを含んでいます。
④ コラーゲン
固い皮や骨をもつハモは、化粧品にも利用されるほど多くのコラーゲンを含んでいます。
コラーゲンは肌や骨を支える物質となり、肌の老化を防ぎます。
ハモの下処理の方法
先ほどもご紹介した通り、ハモを調理する際は「骨切り」という仕事が必要です。
姿のままのハモを購入した時は、包丁でぬめりをこそげ取り、頭とワタを除きます。背びれに沿って包丁目を入れ、背びれを小骨ごと抜き取ってから包丁を逆手に持ち、尾の方から背骨に沿って一気に開きます。
そのあと、皮目1枚残す感覚で、約1mm間隔で身の方に切れ目を入れていきます。
ですが、家庭で処理するのは難しいので、あらかじめ魚屋さんで処理してあるものを買うのが賢明です。
調理時には身がパサパサにならないように、骨切りした部分に刷毛で片栗粉をはたき、余分は振り落としておきます。

ハモのおすすめレシピ
【ハモの梅シソ天ぷら】
ハモはさっと熱湯をくぐらせて梅肉酢を添えていただくのが一般的ですが、叩いた梅肉、大葉とともに天ぷらにしてもおいしく召し上がっていただけます。背びれや背骨もじっくりと揚げて骨せんべいに、ともに絶品ですよ。
【材料】
・ハモ(骨切りしたもの) 1匹分
・梅干し 2個
・大葉 ハモ切り身の数
・片栗粉 適宜
・てんぷら粉 適宜
・揚げ油 適宜
【作り方】
① 梅干しは種から身を外し、包丁で叩いておく。大葉は洗って余分な軸は切る。
② ハモの骨は適度な大きさに切り、血液などを洗い流してしっかりと水分を切り、てんぷら粉をまぶしておく。
③ ハモは身の方に刷毛で片栗粉をはたき、皮の方に梅肉をすこしずつスプーンやヘラで乗せる。
④ 大葉は片面にてんぷら粉を薄くつけ、つけた面にハモの皮の方を乗せる。

⑤ 揚げ油を鍋に入れ、②のハモの骨や背びれを入れてから火にかけ、ゆっくりと180℃まで温める。

⑥ 背びれと骨はカリカリになるまで揚げ、油を切って塩(分量外)をふる。
⑦ てんぷら粉をパッケージの指示通りに水で溶いて③のハモにつけ、3分程度揚げる。
⑧ 器に盛り、好みで抹茶塩を添える。ご飯に乗せ、出汁茶漬けにしてもおいしい。

ハモレシピまとめ
真っ白で脂がのっているにも関わらず、淡白な美味しさが魅力のハモ。魚へんに豊と書くとおり、栄養豊富な魚で、薬膳では関節痛や手足のしびれを鎮め、皮膚を保護し、老化防止に役立つとされています。
日焼けなどで夏の肌は荒れやすいものですが、ハモを食べて、きれいな肌でひと夏を元気にすごしたいものですね。