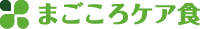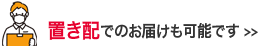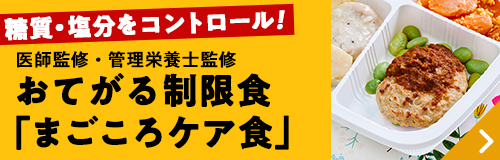四季を問わず、添え物に便利なししとう。中には特別辛いものがあったりして、驚くこともしばしばですね。まるでロシアンルーレットだ!と、子どもの頃ドキドキしながら召し上がったかたも多いのではないでしょうか?今回はそんなししとうの栄養価やメイン料理にもなるおいしいレシピをご紹介します。
目次
ししとうとは
ししとうは、その見た目どおり、ピーマンや唐辛子の仲間で、ナス科トウガラシ属の甘味種に含まれる野菜です。シシトウの祖先である唐辛子はメキシコ中東部が原産で、紀元前8000年頃にはすでに栽培されていたのではないかとされています。
その後、コロンブスによるアメリカ大陸発見ののち、ヨーロッパへと伝えられました。ヨーロッパではさかんに品種改良がおこなわれ、辛味のないものや大きなもの、小さなものとさまざまな品種が誕生しました。
日本には16世紀頃に辛味がある唐辛子が薬味用として伝えられます。時を経て、江戸時代には甘味種が伝えられたようで、各地で品種改良が進み、京都府の万願寺唐辛子、伏見唐辛子、奈良県のひもとうがらしなど、さまざまな地場野菜として新しい品種が登場しました。
しかし、一般にはなかなか定着せず、広く食べられるようになったのは第二次世界大戦後、洋食が多く食べられるようになってからのことです。
ししとうの生産量は1位が高知県で、2017年のデータでは3,200トン、2位が千葉県の968トン、3位が和歌山県の381トンと続いています。
ししとうという名前は、前か見たときにしし(獅子)の顔に似ているから、ということです。
ししとうの栄養価とは
① βカロテン
βカロテンは体内でビタミンAに変化します。ビタミンAは発育を促し、皮膚や粘膜を保護して免疫力の向上を担っています。また、目の網膜の主成分であるロドプシンという物質の原料になり、薄暗いところでも光を感じ、視力を維持する作用があります。
また、抗酸化作用があるため、アンチエイジング効果も期待できます。
② ビタミンB6
ビタミンB6は食材に含まれるたんぱく質からエネルギーを生産したり、皮膚、筋肉や血液を生成したりすることにかかわっています。そのため、不足すると口内炎、湿疹ができたり、貧血が見られたりします。
③ ビタミンC
ビタミンCはコラーゲンの形成に欠かせないビタミンで、皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあります。
また、鉄分の吸収を助け、抗酸化作用が高く、動脈硬化や心疾患の予防を担っています。
ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、毎日摂取する必要があります
④ ピラジン
ししとう、ピーマンなどに特有の青臭いともいえる香り、このもとになっている成分をピラジンといいます。
ピラジンには血液をサラサラにする働きがあります。そのため、血行を促進して体を温め、血栓および血液凝固の予防に役立っているということです。
⑤ カプシエイト
ししとうやピーマンなど、辛くないタイプの唐辛子に含まれている成分です。これは、本来唐辛子に含まれる「カプサイシン」という辛み成分とよく似た性質で、辛味がほとんどないにもかかわらず、腹部脂肪蓄積抑制効果、体重増加抑制効果があることが、味の素株式会社より発表されています。
ししとうの選び方と保存方法
皮に張りがあり、きれいな緑色でヘタの切り口がしなびておらず、きれいなものを選びましょう。時折混じっている辛味が強いものはいわゆる先祖返りで、栽培環境によるものが多いということです。形がいびつで種が少ないもの、小さく、緑色が濃くて黒っぽいもの、猛暑の中栽培されたものは辛味が強く出る傾向にあるといいます。
保存する場合は軽く湿らせたキッチンペーパーなどに包んでから冷蔵庫の野菜室に入れ、できるだけ早く使い切りましょう。
ししとうのおすすめレシピ
【ししとうのはさみ焼き】
細くて小さいししとうは副菜や彩り野菜としてよく利用されていますが、中の空洞部分に肉や魚介で作った団子を詰めて焼いてもおいしいものです。
ほっそりとしているので、お弁当の中に入れるのにもよいですね。
【材料】
・ししとう 10本
・豚ひき肉 100g
・卵 1/2個
・しょうが 1/2かけ
・長ねぎ 1/4本
・塩 1つまみ
・しょうゆ 大さじ1
・みりん 大さじ1
・片栗粉 大さじ1
(肉団子用)
・片栗粉 適宜
(打ち粉用)
・サラダオイル 適宜

【作り方】
① 長ねぎ、しょうがはみじん切りにしておきます。
② ししとうは余分な軸を切り取り、縦に1本裂け目を入れ、必要に応じてワタを取り、内側に刷毛で片栗粉をはたいておきます。

③ ボールまたはビニール袋に豚ひき肉、片栗粉、塩、①の長ねぎとしょうがを入れてよく練り、②のししとうの内側に詰めます。肉団子の表面にひび割れがあると、そこから肉汁が漏れ出てしまうので、サラダオイルをつけた指でなでて滑らかにならします。

④ フライパンにサラダオイルを熱し、③を肉の面から焼きます。途中裏返し、全体に火が通ればみりん、しょうゆを加えてからめるように煮詰めます。

まとめ
小さくて青臭い香りが特徴のししとう。子どもの頃はあの香りや苦みが苦手だったけれど、歳を重ねるにつれ、この味の良さがたまらなく好きになった、という方も多いのではないでしょうか?
中医薬膳学では体を温め、目の疲れや高血圧、口舌炎を予防する効果があるとされています。
猛暑ではあっても、エアコンなどで私たちの体は夏でも冷えていることが多くあります。ししとうを食べて冷えや血行不良を改善し、健やかにお過ごしくださいね。