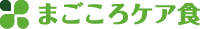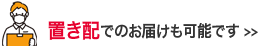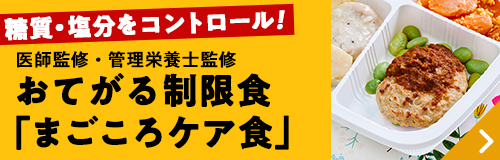涼やかな見た目と、つるっとした食感やのど越しがたまらない食べ物、じゅんさい。夏の季語とされ、生のじゅんさいは旬を迎える6月~8月だけの食べ物ですが、水煮や酢漬けのものは通年見ることができます。全体の98パーセント以上が水分で構成されていることから、あまり栄養はないのでは?と思われるかもしれませんが、実はポリフェノールや食物繊維などが含まれ、健康食材としても注目を集めています。今回は、そんなじゅんさいの栄養価や夏におすすめのレシピをご紹介します。
目次
じゅんさいのレシピや歴史
じゅんさいはハゴロモモ科ジュンサイ属に分類される植物の一種。淡水の池や沼に自生し、水底から水面に向かって茎をのばして、スイレンのような葉を広げます。水中の茎から伸びてくる新芽が、わたしたちが「じゅんさい」と呼んでいる食べ物です。
アジアやアフリカ、アメリカ、オーストラリアなど世界中に分布していますが、食用としているのは主に日本と中国です。中国では薬膳料理にも使われており、体の熱を冷ます食材として親しまれてきました。
日本での歴史も古く、西暦600年ころには食べられていたとされています。奈良時代末期の和歌集「万葉集」にも、心の揺れ様を例えて「蓴菜(なぬは)=じゅんさい」のようだ、と詠んだ一首が残されていました。現在では和食によく使われる食材の一つとなっていて、じゅんさいの生産量日本一の秋田県三種町では、鍋や天ぷら、デザートにまで使われています。
収穫期は4月~9月で、時期によっては生でも食べることができます。スーパーなどで手に入るものの8割は中国産が占め、残り2割の日本産のほとんどを秋田県三種町が生産しています。栽培には適した環境と良質な水が必要なため、日本の一部地域ではすでに絶滅してしまったり、地方公共団体により絶滅危惧種に指定されたりしている場所もあり、貴重な食べ物となっています。
じゅんさいの選び方
じゅんさいは、おおまかに2つの形で販売されています。1つは鮮やかな緑が美しい「生」の状態。食べるには下準備が必要で、沸騰した湯に投入し、1分ほど茹でて素早くざるにあげ、冷水で冷やす必要があります。もう1つは「水煮」や「酢漬け」で、瓶詰めや袋詰めで売られているもの。こちらは袋から出してすぐに使えますが、酢漬けの酸味が気になる方は食べる前に水に30分以上つけ、酢抜きしておきましょう。
食感を楽しむならやはり新鮮な生のじゅんさい一択ですが、手に入りやすさや準備の簡単さを求めるなら水煮や酢漬けもおすすめです。
じゅんさいは水分が多い食べ物なので、購入したらできるだけ早く召し上がってください。水煮や酢漬けでも開封後はすぐに調理しましょう。
じゅんさいの栄養価
ポリフェノール
ポリフェノールは、じゅんさいの緑色のもととなっている色素成分。緑茶などにも含まれることで知られ、優れた抗酸化作用を持っています。脂肪の蓄積を抑制し、コレステロール値を低下させるはたらきがあるため、生活習慣病予防や、動脈硬化・心疾患の予防にも効果的です。加えてコラーゲンなど美肌に役立つ物質の分解を抑える作用も報告されており、たるみやしわの発生を抑制する効果も期待できます。
βカロテン
βカロテンもじゅんさいの緑色を作る色素成分です。抗酸化力があり、免疫を元気にする作用もあるため、アンチエイジングにも効果的です。また人間の体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康を維持し、細胞の正常なはたらきを保つ役割も果たします。
じゅんさいおすすめレシピ
【じゅんさいおろし蕎麦】
見ているだけで涼しい気分になれるじゅんさい。今回は、食感やのど越しを夏らしく楽しめるレシピ「じゅんさいおろし蕎麦」をご紹介します。
【材料】
・そば 2束
・じゅんさい 1パック
・大根 約5センチ
・大葉 お好みで
・そばつゆ お好みで
1.生のじゅんさいは、沸騰させた湯に入れて一分ほど茹で、素早く冷水にあげて冷やします。酢漬けのじゅんさいは水にさらしておきます。

2.そばは規定の分数で茹で、冷水でしめておきます。

3.大根はおろし、大葉は細切りにしておきます。

4.器にそば、じゅんさい、大根おろし、大葉を盛り付け、冷やしておいたそばつゆを回しかけて完成です。

じゅんさいレシピのまとめ
きれいな水の中で緑色の葉が輝く姿から、「食べるエメラルド」とも言い表されるじゅんさい。抗酸化作用のあるポリフェノールや、免疫を元気にする作用もあるβカロテンなどが含まれており、暑さで食欲がない日の一品料理にも、お酒のお供としてもぴったりです。暑い夏を少しだけ涼しくするためにも、じゅんさいを存分に楽しめるレシピを試してみてくださいね。
記事一覧へ戻る